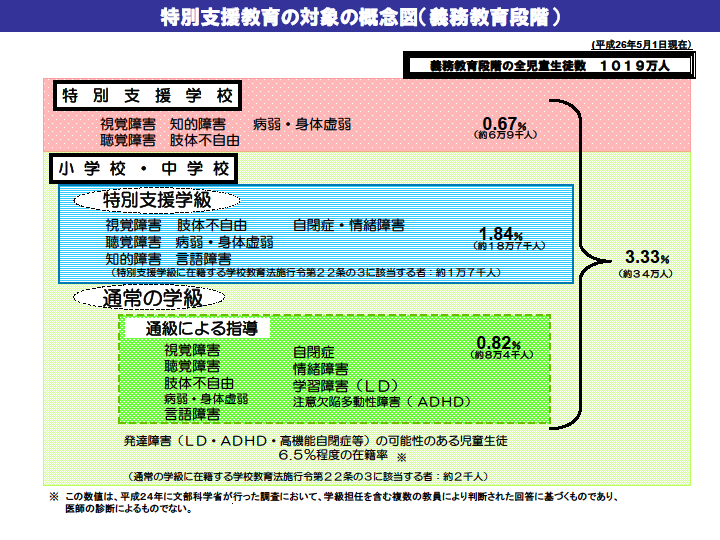障害のある子どもたちが自立し、社会参加するために必要な力を培うため、子ども「一人一人の教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
特別支援学校のみならず、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の通常の学級に在籍する発達障害のある子どもを含めて、障害により特別な支援を必要とする子どもたちが在籍する全ての学校において実施されるものです。
障害のある子どもたちへの教育にとどまらず、多様な個人が能力を発揮しつつ、自立して共に社会に参加し、支えあう「共生社会」の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っています。
昭和19年4月に施行された改正学校教育法により、全ての学校において特別支援教育を推進することが法律上も明確に規定されました。
盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校に変わりました。
制度改正により、
地域のニーズに応じて、設置者(都道府県など)の判断で、一つの障害種に対応した特別支援学校だけでなく、複数の障害種に対応した特別支援学校のいずれもが設置可能になりました。
重複障害のある子どもに、より適切に対応できるようになりました。
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校においても、通常の学級も含め、特別支援教育を行うことが明示されました。
交流および共同学習
障害のある子どもが地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きる上で、障害のない子どもとの交流及び共同学習を通して相互理解を図ることがきわめて重要です。
また、交流及び共同学習は、障害のある子どもにとって有意義だるばかりでなく、小学校・中学校などの子どもたちや地域の人たちが、障害のある子どもたちとその教育に対するただいい理解と認識を深めるための絶好の機会でもあります。
交流及び共同学習は、具体的には、運動会や文化祭などの学校行事を中心に活動を共にしたり、児童会、生徒会活動、総合的な学習の時間、さらには、音楽や体育、図画工作(美術)などの学習においても実施されています。